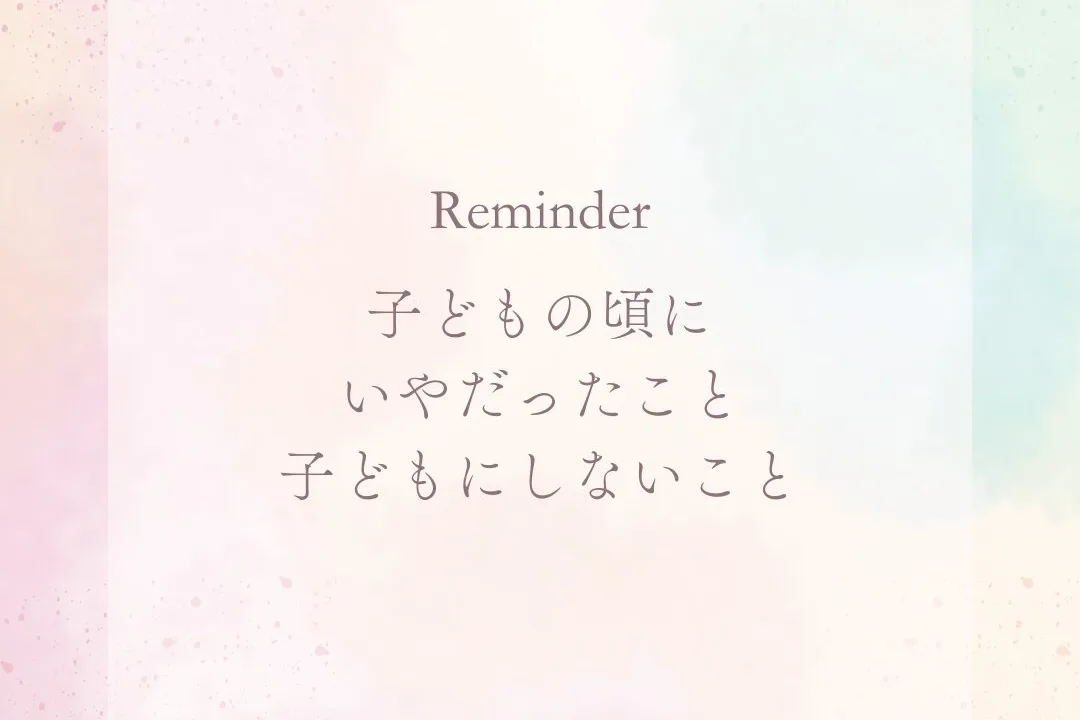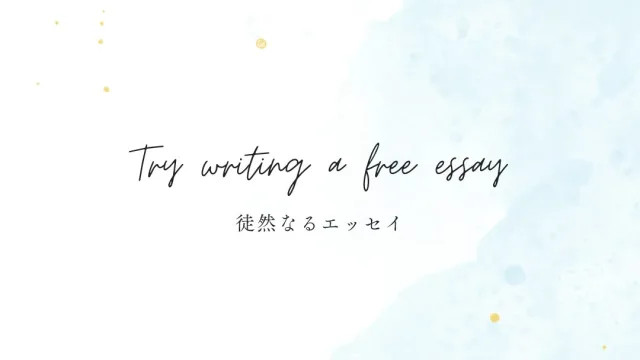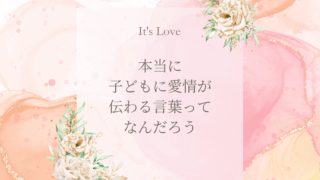子どもの頃にいやだったこと。
自分は子どもにはしないぞ!と固く誓っていたはずなのに、気がつけばついやったりしてるものですよね。
それを書き出すことで、より意識できるのではという試みです。
今回第2弾。
\前回の分はこちらを読んでみてね/
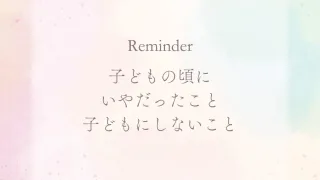
家を継ぐ…とは…?
家を継ぐと言っても、家業があるわけではないんです。
都心よりも少し、そういう昔ながらの雰囲気が強い地域で育ちました。
男の子が産まれれば
「これで跡取りができて安泰だ」
という会話が交わされるのが自然な流れで、昔ながらの考えがまだ根強く残っています。
私の母の実家には跡取りがなく、祖父母(母の両親)は母にお婿さんをもらって家を継いでほしかったのだそうです。
でも父も長男だったため婿入りできず、泣く泣くお嫁にだしたと。
だから私と弟は、ことあるごとに母の実家の名字や家を継いでくれたらなぁと母方の祖父母から言われていました。
この名字を継ぐ血縁者は、この世にもういないんだと。ご先祖さまからいただいた土地も守っていく者がいないんだと。
その祖父も、2年前に他界しました。
子どもは期待にこたえたい
子どもの頃、おじいちゃんっ子だった私は、
そっかぁ、大好きなじいちゃんたちが喜ぶなら、名字変えるのもいいのかもな
とぼんやり思っていた時期もありました。
子どもは純粋に、大好きな家族がよろこぶことはうれしいし、ほめられたいし、なんでもやりたいって思ってしまうんです。
でも。
成長するとその言葉がものっすごく重くなります。
結局私は、大学進学とともに家を出てそのまま就職。
その後すぐ結婚もしたので、家に戻ることはありませんでした。
家族のことも、じいちゃんのことも大好きだったけど、実家のある地域の閉鎖的な感じが耐えられませんでした。
夫との結婚でも、お婿に入ってもらうことは考えられませんでした。
(夫は二男だったけど言い出せなかったです)
ずっと引きずってる申し訳なさ
家をでてから20年以上経ちますが、
家族を裏切ってしまった、期待にこたえられなかった…
そんな思いがまだずーっとあって心に引っかかっています。
家族は面と向かって責めるようなことはしませんが、申し訳ないという気持ちが消えることはないです。
子どもの将来にとってあまり重いことを小さい頃から言い続けると、子どもがやりたいように羽ばたく自由を奪ってしまうんですよね。
無理やりな雰囲気じゃなかったとしてもも、心に鎖がかかるこの感じ。
身をもって体験してるから、息子たちにはこの先も跡取りとか言わないつもりです。
NO MORE 跡取り発言
あとね、子ども=跡取りって言うの、もうやめてほしい。
これは子どもの頃じゃなくて自分が長男を産んだ時の話ですが、義父から
「これで我が家は安泰」
って言われたのが、どうしても許せませんでした。
産後でガルガルしたたのもあるけど、今思い出してもいやだ〜!
なんだか子どもを跡取りっていう道具みたいに考えてる感じが、すごく違和感で。
自分も子どもの頃から「跡取り」と言われてきて、自分の価値はそれしかないのかなって傷ついていたんだろうなと思います。
もちろん、頭ではわかるんです。
自分でがんばってきた家も名字もなくなるさびしさ。
赤ちゃん産まれてよかった!おめでとう!の代わりの社交辞令だってことも。
けどもう戦国時代じゃないんだから、子どもをそういう鎖でしばるのはやめよう。
子どもって、言えばいうほど反発しますよ、たぶん。
期待しすぎないくらいがちょうどいい
子どもには期待しないくらいがちょうどいいんだろうなぁと常々思います。
身近なところでも「将来は子どもに面倒みてもらいたい」という話を聞いたりするのですが、それはかなりのプレッシャーになるはず。
子どもの頃から言われていたらなおさらです(洗脳ともいう)。
私は今のところ、将来住む場所などは子どもの自由と思ってしばるようなことは言っていないつもりです。
自分の老後は自分でなんとかできるように今から考えなくちゃなと思い始める40代、心のつぶやきでした。
\シリーズのほかの記事はこちらからどうぞ/
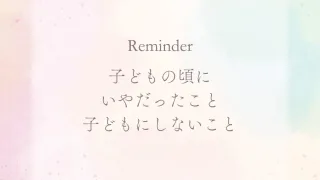
にほんブログ村
フォロー&シェアで同じ思いのあなたとつながれたら…うれしいです☺︎
\マイミとつながってみる?/
Follow @maimi_cocohare